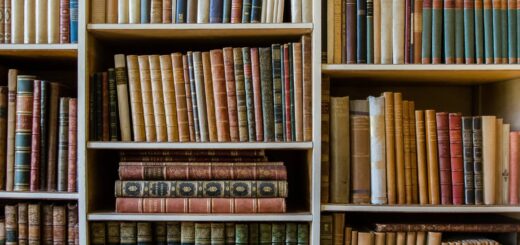子供が家出したら最初にすべきこと。親御さんの具体的な対応

夜、子供部屋を見に行くと、いつもの寝顔がない。机の上には、何かを書き殴ったようなメモが一枚。「もう、家にいたくない」。頭が真っ白になり、心臓がドキドキして、どうすればいいのか分からなくなる。そんな経験をされた親御さんもいらっしゃるかもしれません。
お子さんの家出は、親御さんにとって想像を絶するほどの不安と心配をもたらします。もしかしたら、何か辛いこと、誰にも言えない悩みを抱えているのかもしれません。だからこそ、頭ごなしに叱るのではなく、まずはお子さんの安全を確保し、その気持ちに寄り添うことが何よりも大切です。
この記事では、お子さんが家出してしまったときに、親御さんが取るべき具体的な行動と、頼りになる相談窓口について詳しく解説します。決して一人で悩まず、この記事を参考に、一歩ずつ解決に向けて進んでいきましょう。
まずは落ち着いて、お子さんの安全を確認する
家出に気づいたら、パニックになる気持ちをぐっと抑えて、最初に行うべきはお子さんの安全確認です。
- お子さんの携帯電話に連絡してみる: まずは、お子さんの携帯電話に電話をかけたり、メッセージを送ったりしてみてください。「今どこにいるの?」「何か困ったことはない?」と、心配していることを伝えつつ、冷静に問いかけてみましょう。既読にならない場合でも、何度も連絡することで、お子さんに「心配している人がいる」というメッセージが伝わるかもしれません。
- 普段よく行く場所に心当たりはないか探してみる: お子さんが仲の良い友達の家や、アルバイト先、近所の公園など、普段よく行く場所に連絡を取ったり、直接足を運んでみたりしてください。もしかしたら、感情的になって家を飛び出したものの、いつもの場所に身を寄せている可能性もあります。
- 学校や警察に連絡することも検討する: 数時間経っても連絡が取れない、または事件や事故に巻き込まれた可能性が少しでもあると感じた場合は、速やかに学校や最寄りの警察署に連絡しましょう。学校の先生は、お子さんの最近の様子や人間関係について何か知っているかもしれません。警察には、状況を詳しく説明し、必要であれば行方不明者届を提出することも検討してください。早期の捜索につながる可能性があります。
「家出人は探してくれない?」失踪者捜索の誤解と警察の役割
「うちの子が家出して数日経つけど、警察はなかなか本格的に探してくれない…」
お子さんやご家族、大切な人が突然いなくなってしまった時、一刻も早く見つけ出したいと願うのは当然です。しかし、家出や失踪の届け出をしたものの、警察の動きが鈍いと感じ、不安や不信感を抱いている方もいるかもしれません。
「家出人は警察は探さない」という声を耳にすることもありますが、これは一部誤解を含んでいます。この記事では、家出と失踪の違い、警察が捜索を行う基準、そして家族ができることについて詳しく解説します。
「家出」と「失踪」:法律上の明確な区別はない
一般的に、自分の意思で自宅を出て、所在が分からなくなっている状態を「家出」、事件や事故に巻き込まれた可能性があり、安否が心配される状態を「失踪」と呼ぶことが多いです。しかし、法律上、明確な区別はありません。どちらの場合も、警察に対して「行方不明者届」を提出することになります。
警察が捜索を開始する基準
警察は、行方不明者届が提出されると、その状況に応じて捜索を開始します。しかし、すべてのケースで大規模な捜索が行われるわけではありません。警察が重点的に捜索を行うのは、以下のような場合です。
- 事件や事故に巻き込まれた可能性が高い場合: 目撃情報がある、所持品が不自然な状況で発見された、失踪前にトラブルがあったなどの状況から、犯罪に巻き込まれた疑いがある場合。
- 例: 知人との間で激しい口論があった後に行方不明になった、海岸で所持品だけが発見されたなど。
- 自殺や生命の危険が懸念される場合: 遺書のようなものが発見された、精神的に不安定な状況が続いていたなどの情報から、自ら命を絶つ危険性がある場合。
- 例: 「さようなら」という内容のメモが残されていた、失踪前に精神科に通院していたなど。
- 未成年者や高齢者、病気療養中の人が行方不明になった場合: 判断能力が十分でない未成年者や、健康状態に不安のある高齢者、病気療養中の人が行方不明になった場合は、保護の必要性が高いと判断され、早期の発見に向けて捜索が行われることがあります。
- 例: 認知症の高齢者が一人で出かけて行方不明になった、持病のある中学生が家出したなど。
「家出」と判断された場合の警察の対応
一方、失踪の状況から事件性や生命の危険性が低いと判断された場合、例えば、成人が自分の意思で家を出て、特に心配な状況が見られない場合は、大規模な捜索は直ちには行われないことがあります。
家出から1週間がタイムリミット?警察庁データが示す発見率低下の現実
「もしかしたら、すぐに帰ってくるかもしれない…」
お子さんや大切な人が家出してしまい、そう願う気持ちは痛いほどよく分かります。しかし、警察庁のデータによると、行方不明者の発見率は、家出や失踪から時間が経過するにつれて著しく低下する傾向にあります。特に、1週間という期間は、その後の発見の可能性を大きく左右する重要な分かれ目となることが示唆されています。
この現実は、家出されたご家族にとって、より一層の焦りと不安をもたらすかもしれません。なぜ、1週間を過ぎると発見が難しくなるのでしょうか?そして、この厳しい現実を踏まえ、今、私たちにできることは何なのでしょうか?
警察庁データが示す厳しい現実:1週間後の発見率低下
警察庁の過去のデータを確認すると、行方不明者の発見率は、届け出から時間が経つにつれて明確に低下する傾向が見られます。特に、1週間を過ぎると、生存が確認されるケース、無事発見されるケースともに、その割合が顕著に減少するというデータが存在します。
これは、時間が経過するにつれて、行方不明者の移動範囲が広がる可能性、事件や事故に巻き込まれるリスクの高まり、そして何よりも情報が錯綜し、手がかりを見つけにくくなることなどが要因として考えられます。
なぜ、時間経過が発見を困難にするのか?
- 広範囲な移動: 家出直後は比較的近隣に留まっている可能性もありますが、時間が経つにつれて、遠方へ移動している可能性が高まります。これにより、捜索範囲が広がり、発見が困難になります。
- 情報の希薄化: 目撃情報や行動範囲に関する情報は、時間が経つほど曖昧になり、記憶も薄れていきます。初期段階での迅速な情報収集が重要となります。
- 事件・事故のリスク: 特に若年層や精神的に不安定な状況にある方の家出の場合、時間が経つにつれて犯罪に巻き込まれたり、自ら危険な状態に陥ったりするリスクが高まります。
- 生活基盤の形成: 長期間家出している場合、新たな生活拠点を築き、意図的に連絡を絶っている可能性も考えられます。
しかし、警察は行方不明者届を受理した後、以下のような対応を行います。
- 情報収集: 行方不明者の写真や特徴、家出に至った経緯、交友関係などを詳しく聞き取り、捜索に必要な情報を集めます。
- 関係機関への照会: 必要に応じて、医療機関や福祉施設、交通機関などに情報提供を依頼することがあります。
- 発見時の連絡体制: 発見につながる有力な情報があった場合に備え、家族との連絡体制を整えます。
焦らず、お子さんの気持ちに寄り添う
相談窓口を頼ることはもちろん大切ですが、親御さん自身も、お子さんのためにできることがあります。
- 感情的にならず、冷静に対応する: 家出の原因が分からず、不安や怒りでいっぱいになるのは当然のことです。しかし、お子さんと連絡が取れた際に、感情的に責め立ててしまうと、さらにお子さんを追い詰めてしまう可能性があります。まずは深呼吸をして、落ち着いた声で「心配しているよ」「何かあったの?」と優しく声をかけてあげてください。
- お子さんの気持ちに寄り添う姿勢を持つ: 家出の背景には、お子さんなりの理由があるはずです。「どうして家を出てしまったの?」と問い詰めるのではなく、「何か辛いことがあったんだね」「話せる範囲でいいから、聞かせてくれる?」と、お子さんの気持ちに寄り添う姿勢を見せることが大切です。頭ごなしに否定したり、批判したりするのではなく、まずは受け止めることから始めてみましょう。
お子さんの家出は、ご家族にとって大きな試練です。しかし、決して一人で抱え込まず、様々な支援の手を借りながら、お子さんと向き合っていくことが大切です。私たちは、お子さんが一日も早く安心して家庭に戻り、笑顔で過ごせるようになることを心から願っています。