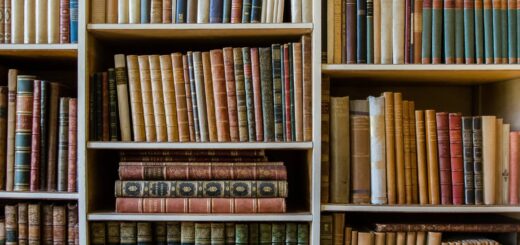耳で辿る明治・大正・昭和:国立国会図書館「歴史的音源」(れきおん)の魅力と活用法

国立国会図書館が提供する「歴史的音源」は、明治・大正・昭和初期(1900年代初めから1950年頃)に国内で製造されたレコード(SP盤)の音源をデジタル化したコレクションです。このコレクションは「れきおん」という愛称でも親しまれています。
「歴史的音源」(れきおん)とは
音源の数と種類:歴史的音盤アーカイブ推進協議会(HiRAC)がデジタル化し、国立国会図書館に納入されています。収録点数は約5万点に上り、そのうち約5,000点がインターネットで公開されています。インターネット公開以外の音源は、国立国会図書館内や、配信提供サービスに参加している図書館・調査研究機関(参加館)で聴くことができます。
収録ジャンル:歌謡曲だけでなく、多様なジャンルの音源が収録されています。上位10ジャンルは以下の通りです。
- 流行歌・歌謡曲(11,464点 / 11,428点)
- 邦楽(10,285点 / 10,281点)
- 落語・漫才・浪曲・講談(6,253点)
- 民謡・国民音楽(日本)(4,898点 / 4,904点)
- 唱歌・童謡(2,637点)
- 器楽(クラシック以外)(2,092点)
- 声楽(1,932点 / 1,923点)
- 教育・児童(1,507点)
- 演説・講演・朗読・実況(1,485点)
- 近代演劇(日本)(1,003点)
有名な音源の例
インターネット公開音源としては、三浦環が歌う『独唱:埴生の宿』、渋沢栄一の『講演:道徳、経済合一論』、東郷平八郎による『講演:連合艦隊解散式訓示』、近衞文麿の『演説 重大時局に直面して』 などがあります。
館内限定公開音源には、ベルリンオリンピックの水上競技実況放送(「前畑ガンバレ」で有名)や、美輪明宏(丸山明宏)の歌唱による『イタリア映画「道」主題歌 ジェルソミーナ』 などがあります。
専門家による紹介:音源の背景や作詞・作曲者、演奏者について紹介する「テーマ別音源紹介」も提供されています。
利用方法と公開範囲
- インターネット公開音源:著作権・著作隣接権の保護期間が満了している音源は、インターネット利用可能な環境であればどこでも聴くことができます。れきおん専用サイト(https://rekion.dl.ndl.go.jp/)から直接アクセス可能です。
- 国立国会図書館・配信提供参加館限定公開音源:保護期間内の音源は、国立国会図書館内および配信提供サービス参加館でのみ聴くことができます。2021年9月現在、参加館数は323館に上り、アメリカやドイツなど海外の参加館も含まれています。
- 検索機能:サイトでは、キーワードによる簡易検索やジャンル別検索、詳細検索が可能です。検索結果から音源タイトルをクリックすると、再生画面で音源を聴くことができます。
- 利用制限(参加館):参加館での利用は、専用端末に限られ、録音・複製・ダウンロード、USBメモリ等の外部記憶装置の接続は禁止されています。
イベント等での活用
「歴史的音源」は、配信提供参加館内であれば全音源(約5万点)を使ってイベントを開催できます。
- イベント事例:石原裕次郎や古関裕而など特定人物に焦点を当てた鑑賞会、紅白歌合戦のプログラムを再現したイベント、上方演芸に関する資料展示と落語音源の組み合わせ、時刻表など鉄道資料の紹介のBGMとして鉄道音楽を流す講演会 など、多様な活用が可能です。
- 許可や広報:イベント開催にあたって事前の許諾は不要です。また、国立国会図書館はイベント内容を参加館へのお知らせや、れきおんサイト上で広報する手伝いも行っています。
- プレイリスト:参加館向けに、連続再生が可能なプレイリストの提供も行っています。
- 大学での活用例:インターネット活用方法の学習素材として、また戦前の社会に実感を伴って接近するため、そして映像が残されていない時代の「音」資料として、大学のゼミで活用された事例もあります。